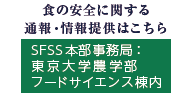[2014年11月18日火曜日]
このブログでは食品のリスク情報とその伝え方(リスクコミュニケーション)について毎回議論しているが、今回は特に食品中ハザードのリスク評価結果が疑わしい状況で、ヒトへの健康被害の懸念が報道されることの問題について議論したい。
最近出版された日本リスク研究学会誌(Vol.24: 111-119, 2014)に、関澤純先生の『リスク評価の明確化と有用性の検討による食品安全ガバナンスの向上』と題した非常に興味深い論文が発表された。この論文の中で、従来の動物試験によるリスク評価の限界とその結果を提示することの問題点を提起され、WHOで長年検討してこられた動物とヒトの生物学的差異や同等性を考慮した新しいリスク評価の手法を提唱されている。
筆者も最近、食品中の化学物質のリスク評価が動物試験のみから結論を導き出されることに関して、本当にいまの暴露レベルでヒトに健康被害をもたらすのかどうか非常に疑わしいケースがあると感じていたので、大いに共感する内容であった。化学物質の毒性評価をする際に、動物試験のデータとヒトでの摂取量をもとに暴露マージン(MOE)を求めるというやり方が既存のリスク評価手法だが、関澤先生によると本来動物試験のデータをヒトへ適用する際に、その作用様式(MOA:Mode of Action)などの違いを考慮しなければ、ヒトでの健康リスクの評価を誤る可能性があると指摘されている。
その実例として、M. Meekら(Appl.Toxicol. 34:1-18. 2014)によると、D-リモネンという香気成分が動物試験で腎臓がんの発がん物質として指摘されたが、実際はこのD-リモネンの代謝物がタンパクに結合して発がん原因の活性体に変化するのは、ラットでは起こるものの、ヒトでは起こらない作用(MOA)であったため、ラットでの発がんデータをヒトには適用できないとの結論が導き出されたとのことだ。
同様の事例として、じゃがいもなど野菜の加熱調理品やコーヒーなどに含まれるアクリルアミドの発がん性が、動物試験の結果をもってヒトでの健康リスクが指摘される報道が散見されているが、これも問題があるということを筆者は過去の論文を引用して指摘したい: E.K.Koppら(Toxicol. Appl. Pharmacol. 235: 135-142, 2009)によると、アクリルアミドは生体内で代謝されてグリシドアミドという活性体になりDNAに結合することで初めて遺伝子毒性/発がん性を呈することが知られているが、ラットではたしかにこの活性体の代謝物が尿中に認められたものの、ヒトではグルタチオン抱合という代謝排泄機能が高いためか、この活性体代謝物がほとんど認められなかったことから、アクリルアミドのヒトでの発がんリスクはきわめて低いであろうとの結論を導き出している。
前述の関澤先生の論文の中でも、ラットでの試験で発がん物質として認められたものに肝臓が標的となったものが多いが、これらの多くがヒト肝臓では発がん性を示さないことも報告されているとのこと。
発がんのメカニズムは、イニシエーション・プロモーション・プログレッションという3つのステップを経て起こると言われているが、いわゆる動物試験で遺伝子毒性を呈すると言われる発がん物質は、このイニシエーションステージでDNAに活性体が結合してDNAアダクツを形成することで発現する。だが、実際発がんにまで至るためには、プロモーション・プログレッションステージに影響を与えるホルモン作用、局部の炎症、ウィルスの増殖などの方が、発がん予防やがんの抑制と言う意味からは重要なのではないかとの考察をされている。
筆者もこの点には同感であり、天然物である食品中の多種多様な成分が、発がんの複雑なメカニズムに対してどう作用するか(助長するのか、抑制するのか、無作用なのか)に関して単純な回答があるとはとても思えず、ある単一化合物が動物試験で遺伝子毒性を発現したというデータのみをもって、その成分をわずかに含む食品が「ヒトで発がん性あり」と断定したような結論を導き出すのは飛躍が過ぎるのではないか。
たとえば、その食品に抗酸化物質などが含有されていれば、抗炎症-抗プロモーター作用をもって、遺伝子毒性の認められた発がん物質の作用が相殺され、ヒトでの発がん性を呈さない結果となっても全く不思議はないのである。
これらの文献情報を読めば読むほど、動物試験の発がん性データのみをもって、ヒトでの発がん性をリスク評価することの危うさを感じるが、ではヒトでの発がん性をいかにして評価すればよいのだろうか? やはり筆者は、ヒトでの疫学調査が、その食品を継続的に食することのヒトへの健康影響を評価するのに最も適した科学的エビデンスではないかと考えている。
ただ、その疫学調査データについても、前向きまたは後向きコホート研究、症例対照研究など、それぞれの手法に特徴があり、当該食品の摂取量と発がん率の相関に関して、たしかに因果関係が考察できているかどうかなど、厳しい目で査読をしたうえで、総合的考察をもってその食品または食品成分の発がん性を評価すべきであろう。
前述のアクリルアミド(AA)に関する疫学調査研究を調べてみると、多数の報告があるが、そのほとんどがAA摂取量と発がん率との間に「相関なし」との結論であった。「相関あり」とした論文もいくつかあるが、1980年代の疫学調査で正確なAA摂取量が把握できていたとは思えない研究、AA摂取が多い群は明らかにカロリーや脂質摂取も多い研究、喫煙者が含まれるサブコホートで相関をみたものでは喫煙自体にAAがどのくらい含まれたか不明の研究などなど、研究方法自体に問題が散見された。
現時点ではやはり、AAと発がん率の間に明確な相関は見いだされておらず、動物試験の結果がそのままヒトに適用できているとは言えない。
このようにある単一化合物の動物試験結果から、食品自体のヒトへの発がん性など健康影響をリスク評価することには無理があり、ある意味結論の出ていないリスク評価結果をもとに不特定多数の消費者にむけて報道することには大きな疑問を感じる。しかも、このようなリスク評価結果を報道される際の見出しが、食品中の化学物質名ではなく、「食品そのものの発がん性」となると、大きな風評被害をもたらすのは間違いない。「ヒトでの発がん性はよくわかっていない、と○○教授が言っている」というような報道の仕方も、典型的な不安煽動因子なので、その報道が風評被害をよぶとの認識を強くもっていただきたいものだ。
SFSSでは、食品のリスク管理やリスコミ手法についてコンサルティングや学術啓発講演のサービスを提供しており、11月28日(金)には、「食の安全と安心フォーラムⅨ ~我が国における食物アレルギーの現状とリスク管理②~@グランフロント大阪オカムラショールーム(JR大阪駅前)」を開催します。ふるってご参加ください。
⇒ http://www.nposfss.com/cat2/forum09.html
(文責:山崎 毅)